エリアごとに特色のある札幌の歴史
こんにちは、えぞまち歴史部です。
札幌の歴史的建造物といえば、観光スポットとして名高い「時計台」や、中島公園にある「豊平館」、大通公園にある「札幌市資料館」などが有名です。
札幌の「中心部」として位置づけられた歴史についていえば、江戸時代に「さつほろ」の名で呼ばれているのは現在の中央区よりも北で、北区茨戸周辺といわれています。
現在の中央区・大通近辺や札幌駅のような中心街が形成されたのは、明治維新後、島義勇による札幌本府の建設からですね。
もともと北海道の「中心地」という位置づけのはじまりは札幌ではなく、貿易港としてすでに開発されていた箱館がその役割を担うものと考えられていたのですが、島義勇の「五州第一の都(世界一の都市)」を建設するという構想から、現在の札幌の基礎となる碁盤の目状の市街地が形成されていったわけです。
また、明治以降「屯田兵」の制度が開始され、北海道の開拓と守備という役割が重要視された頃には、西区琴似地区がその先駆けとなりました。
このように、ひとくちに「札幌の歴史」といっても、エリアごとにそれぞれ異なった経緯で発展し、街が形成されてきたことがわかります。
さて、今回注目したのは、札幌市南区エリアの歴史と「札幌軟石」という石材についてです。
スポンサーリンク(広告)
歴史的建造物にたびたび登場する「札幌軟石」とは?

札幌近辺の歴史的建造物を訪れたことがある方にとっては、「札幌軟石」という用語は馴染み深いものであるかもしれません。
たとえば先にも紹介した「札幌市資料館(旧札幌控訴院)」や、北海道大学農学部のサイロ、小樽運河の倉庫などにも札幌軟石が使用されています。
現代の建造物では、住宅をはじめほとんどの建物はコンクリートを使用して建造されますが、一定の品質のコンクリートブロックが工業的に生産され、かつ輸送体制なども整い本格的に活用されたのは昭和30年代以降といわれており、それまでは「石材」は建造物をつくる際に欠かすことのできない資材であったのです。
こうしたことから、札幌軟石は札幌周辺の地区にとって重要な資材であり、採石場は資源の採取拠点であったことがわかります。
もちろん、採取した石材を加工場へ、あるいは加工した石材を利用する地点まで輸送するような交通網も整えられていきました。(これが「定山渓鉄道線」※現:「じょうてつ」のかつての鉄道路線※ の重要な役割のひとつでした。)
札幌軟石が活用されるようになった背景とは?
札幌軟石は、そもそもどこからきた石なのでしょうか?その由来は約4.4万年前まで遡る、「支笏大噴火」であるとされています。

「支笏」といえば支笏湖ですが、支笏湖はこの支笏大噴火の際に形成されたカルデラ湖で、このときに噴出した軽石・火砕流が冷えて固まったもの(溶結凝灰岩)が「札幌軟石」と呼ばれる石です。
この札幌軟石を発見したのが、明治時代に来日したアメリカ人の土木技術者「A・G・ワーフィールド」と、鉱山技師の「トーマス・アンチセル」でした。
札幌軟石のもつ「切り出しの容易さ」や「保温性の高さ」から、建造物をつくる際の資材として大々的に活用されるようになったというわけです。
現在の「札幌軟石」の利用
もちろん、先に述べたように現代では建物をつくる際にはコンクリートを用いるのが一般的です。
ただし、札幌軟石の採石は途絶えたわけではなく、現在でも採石・加工が行われています。
愛好者は建造物に利用したり、墓石としての利用もあります。
また、端材が雑貨・インテリアとして活用される例もあり、今回訪れた「ぽすとかん」ではそうした雑貨の一部に出会うことができます。
スポンサーリンク(広告)
札幌軟石で作られた旧郵便局「ぽすとかん」

さて、今回えぞまちで訪れたのは、南区石山にある「ぽすとかん」という建物です。
この建物はもともと、石山郵便局として利用された建物で、札幌軟石が使われています。
「石山郵便局」の前身となる「穴の沢郵便局」が開設されたのは明治35年(1902年)のことで、「石山郵便局」という名前に改名されたのは明治41年(1908年)のことでした。
札幌軟石が使われた、現在に残る形の建物は、昭和15年(1940年)に改築されたものです。
天井のアーチ部分は、当時かなり注目を集めたよう。オシャレですね。
その後も郵便局として活躍を続けた建物でしたが、昭和49年(1974年)には、この建物は郵便局としての役割を終えることになりました。
平成17年(2005年)には、札幌景観資産第5号に指定されたものの、建物は個人所有のものであり、維持管理にも苦労されていたところ、有志による「ぽすとかん再生プロジェクト」が始動し、クラウドファンディングなどを経て、現在の「ぽすとかん」が残っているのです。
「ぽすとかん」には何がある?

「ぽすとかん」内部に入ると、1F部分には「軟石や」と「ニシクルカフェ」があります。

右手にはニシクルカフェ、少し奥まっている雰囲気が素敵ですね。
「ニシクル」というのは、アイヌ語で「雲」という意味だそう。
コーヒーのほか、自家製酵母のベーグル、「ニシクルカレー」などのメニューが楽しめます。


そして、左手にあるのが「軟石や」です。
ここでは、札幌軟石を使った雑貨品が販売されています。
この軟石雑貨ですが、アロマを垂らすことで「アロマストーン」としても使えるとのこと。
建物もバリエーションがあり、まったく同じものではないというのがオリジナル感があって良いですね。

今回えぞまちでは、こちらの「教会」型の軟石を購入させていただきました。

こちらはネクタイピンなどの装飾品です。軟石とアクセサリーという組み合わせ、とてもオシャレです。

ふと手に取ったこちらは、一見すると、採石場で石を切り出しているイラストが描かれているポストカード。イラストももちろん素敵なのですが…!

裏面に、「イラストが動きます!」との説明が。お店の方に方法を教えていただき、自宅で実践してみると…
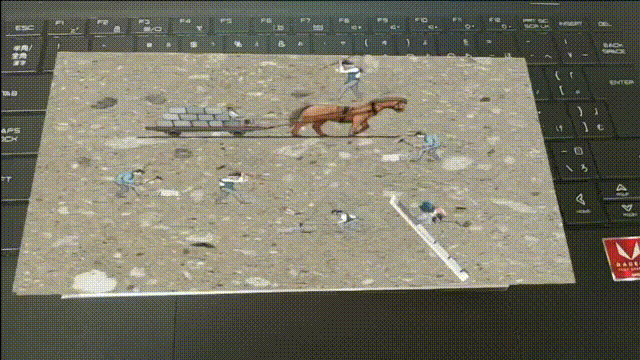
このように動きました!InstagramのARエフェクトを利用した機能で、表面のイラストをトリガーとして、ARエフェクトを起動させているわけですね。す、すごい…!

2Fへの階段の途中には、「札幌市都市景観賞」の表示と、

壁には一面の札幌軟石!こちらも壮観です。

2Fには腰掛けられるスペースがあり、イベントスペースも併設されていました。
広さの限られている建物ですが、空いているときはゆったりできそうな雰囲気です。
なお、「ぽすとかん」を訪れた際の動画をYoutubeにて公開しております。
![]() <ライラックマも喋ります!
<ライラックマも喋ります!
「ぽすとかん」の向かいには、「旧定山渓鉄道 石切山駅」

ぽすとかんを出て、平岸通を挟んで向かいには、「石山振興会館」があります。この建物は、かつての定山渓鉄道駅で、「旧石切山駅」との表示があります。
当時の鉄道は白石駅からおおまかに豊平-澄川-真駒内-石切山-簾舞-小金湯-定山渓というルートを1時間30分で運行していました。
定山渓温泉との間の温泉客輸送のほかにも、先に解説したように鉱石・石材・木材の輸送が重要な役割でした。
1957年ごろには、定山渓鉄道は東京急行電鉄(東急)の傘下に入り、”札幌都市圏の私鉄統合”、”定山渓鉄道線・夕張鉄道線の延伸”、”札幌と江別の間に「札幌急行鉄道」の新設”などの構想があったようですが、創業者、五島慶太氏の逝去によって実現しなかったようです。
現在では、小金湯・定山渓エリアを除けば地下鉄南北線と東西線が各エリアを繋いでいるという状態ですね。


とはいえ、戦後のいっときは温泉利用とビール券・枝豆・とうきびがセットになった「月見電車」なる豪勢なセットプランもあったようですから、当時の人々は定山渓鉄道を使って定山渓温泉に入るというのは大きな楽しみだったのでしょうね。

なお、旧石切山駅の並び、石山交番の隣には、平成11年(1995年)に設置された、札幌軟石製の「石切山街道碑」があります。
スポンサーリンク(広告)
おわりに

今回は、「札幌軟石」、「定山渓鉄道」、という大きなテーマから、「ぽすとかん」と「旧石切山駅」という建物を訪れてみました。
定山渓というと、現代では温泉が真っ先に思い浮かぶのですが、札幌の歴史において札幌軟石や定山渓鉄道が果たした役割は非常に大きなものだったと感じさせられました。
そうした歴史の背景を知る意味でも、また、単に「札幌軟石を使ったアクセサリーやインテリアを楽しむ」という意味でも、「ぽすとかん」は大変魅力的なスポットですので、ぜひ訪れてみてくださいね。
施設情報

○施設名:ぽすとかん(旧石山郵便局)
○住所 :〒005-0842 北海道札幌市南区石山2条3丁目1−26
○URL :https://www.postokan.com/
○地図 :
○施設名:石山振興会館(旧石切山駅)
○住所 :〒005-0841 北海道札幌市南区石山1条3丁目1−30
○地図 :
○施設名:石切山街道碑
○住所 :〒005-0841 北海道札幌市南区石山1条3丁目1
○URL :https://www.city.sapporo.jp/minami/ishibumi/chiku0701.html
○地図 :
スポンサーリンク(広告)